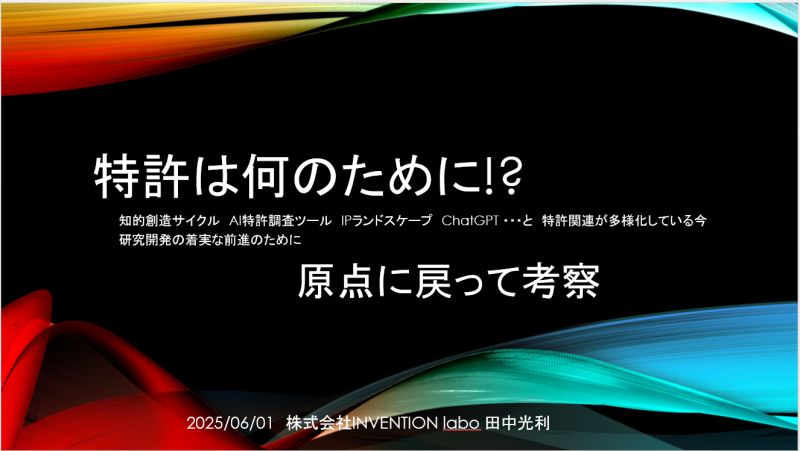--------LinkedIn2か月前の投稿(抜粋)です---------
<概要>
先行技術を知らなければ良い発明は出来ないから、まず先行技術の調べ方について整理してみた。先行技術の調べ方(特許調査)にはIT化の波が2度訪れたと見ることができる。第一次の波は紙媒体から電子データへの移行だった。この波は現在完結し紙時代には想像できなような様々な発展をもたらした。第二次の波はAI化だ。まだまだ課題が多い。
<詳細>
第一次IT化の波
~調査工数(作業部分)が1/10以下に~
特許に含まれる技術情報を効率的に取り込んで研究を進めると他社より早く参入できる可能性が高くなる・・これは経験的に良く知られた事だ。
特許公報が紙であった時代でも一早く特許検索システムを導入して優位性の維持に努めてきたメーカー様も多いだろう。この時代の検索は専任者が行い、印刷出力された抄録を元に一覧表を作成し図書へ行って公報をコピーした。相当手間がかかるため外注により公報を入手する事も有った。このニーズを反映して公報番号リストをFAXすると紙公報を郵送してくれる文献サービス会社が複数存在した。
しかし1990年に特許公報が電子化されると状況は一変した。大手電気メーカー傘下のIT企業が特許庁から電子データの提供を受け各社独自方式の商用データベースを構築した。特許庁も世界最大のデータベースと呼ばれた電子図書館(現在のJ-PlatPat)を無料で公開した。その結果、研究者様はご自分の机で実験データを見るのと同程度の手間で特許明細書が閲覧できるようになった。
第二次IT化の波
~調査工数(思考部分)を減らせるか?~
特許を調べようと思ったら、まず自分のPCでデータベースを開くだろう。図書へ行って紙公報を借りてくるような人は恐らくいない。つまり第一次IT化はその圧倒的な効果が研究現場に受け入れられ根付いたと言える。
さて、第二次IT化はどうだろう。キーワードは人工知能AIの活用だ。
「集めた明細書を人手によらず整理できる」
「本発明の特許性を否定する資料を瞬時に抽出できる」
と謳う事業者が多数出現し、
「トライアルをやってみませんか?」
「講習会に参加しませんか?」とお誘いを受けた。
しかし、すごく期待して参加するも結果はよろしくなかった。
その後もウォッチしているが
現在までに、特許調査を置き換えられるツールには出会えていない。
●部分的な活用は可能●
A社のシステムはその特徴を理解するといくつかのユニークな使い方が可能だ。特に新規テーマを考えるときなど、この「使い方」を知っているとアイデア出しやリスクチェックに活用できる。A社はシステムの原理と、出来ること・出来ないことを明確に教えていただけるし無料で試すことも出来る。A社の創設者には「研究者を楽にしたい」との強い思いがあり、その姿勢が全社に浸透している。
●トライアル有料の事業者●
一方、B社やC社は映画のオープニングのような立派なプレゼンが特徴だ。またキャッチも「世界の特許が一瞬で調べられる」「新規性進歩性も判断できる」など、ついにここまで来たかと期待が膨らむものとなっている。しかし実例などは具体的には教えていただけない。質問をすると営業担当の方から連絡が入り自分たちには専門的なことはわからないからトライアルで判断してはと勧められる。申し込もうとすると数十万を要求され驚いた。実際に何ができそうか可能性を確認するだけでも骨が折れる。
●不適切な例●
「特許調査会社に無効資料調査依頼したがAIツールで有効な資料が見つからなかった」という相談を受ける事がある。
調査報告書を見てみるとスコア(明細書に含まれる類似単語の出現頻度)でソートした表が付されている。一番スコアが高い明細書が一番有効な無効資料だという前提になっている。素人か?と思いたくなる。対象請求項の要件が明細書のどこかに本発明として記載されているものが無効資料であって、単語が類似している資料とは限らない。特に公知例を組み合わせて進歩性を否定する時は、二つ目以降の公知例は、対象特許とはだいぶ違うことが多い。この事は無効資料調査を適切に行っている方なら当然知っている事だ。この特許調査会社の調査員が無効資料調査や使用しているAI特許調査ツールの特性を理解されているか疑問を感じた。
●前提が間違っている?●
あるシステムの説明会に出ると原理的な説明があった。「当システムは特許を自然言語として演算処理を行います・・・」すると会場から「特許は自然言語ではないのでは?」との指摘が出た。説明者は何も答えなかった。特許の文章は大変読みにくい。請求項には1文がA4サイズ1枚を超えるような長いものも存在する。普通の話し言葉や書き言葉とは著しく異なっている。この会場の指摘が的を得ていたのか、最近はこの事業者様のホームページから特許調査ツールの紹介が消えている。問題があったのだろう。
●ブラックボックス?●
あるシステムの担当の方と打ち合わせした。やるたびに結果が違うから間違いの原因を特定できない事をお話しし、どのような原理で動作しているのか、と聞いた。その方は原理を抑えていないようだった。それを正直に言わず、歯切れの悪い打ち合わせになった。おそらく心臓部は自社開発ではなく米国のものなのだろう。だとすると他社と同じ問題を持っている。